【転職のポイント】診療科目選びで変わるキャリアと働き方
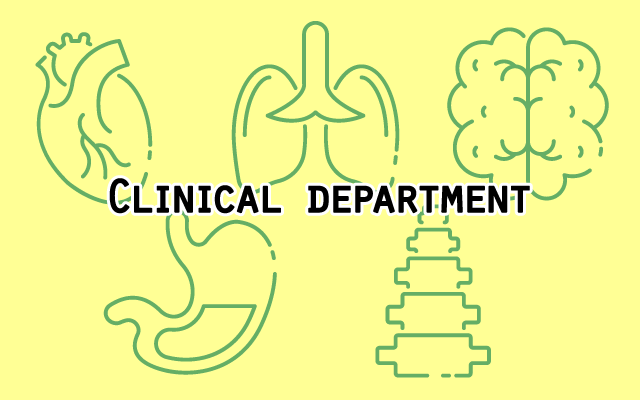
「医療事務の仕事がしたい」という漠然とした希望から、医療事務への転職を考える人もいると思いますが、医療事務の仕事内容や働き方は診療科目によって大きく異なります。
本コラムでは転職活動の重要な検討ポイントとなる「診療科目の選択」に焦点を当てて、各診療科目の特徴や医療事務としての業務内容の違いについて解説します。
医療事務の転職で診療科目選びが重要な理由
医療事務の仕事内容は一般的に受付、会計、診療報酬請求、カルテ管理などが主な業務とされています。
しかしこれらの業務内容は診療科目によって異なり、必要とされるスキルや適性も変わってきます。
診療科目によって異なる業務内容
診療科目ごとに診療の特性、受診者層、診療の流れが異なるため、医療事務の業務内容にも違いが生じます。
例えば整形外科では画像検査の取り扱いが多い一方、皮膚科では処置や外用薬の取り扱いが中心になるなど、診療報酬請求の内容も異なります。
受診者層の違いによる対応の差
小児科では子供とその保護者、眼科では高齢者が多いなど、診療科によって主な受診者層が異なります。
そのため、求められる接遇やコミュニケーションスキルにも違いがあり、自分の適性に合った診療科目を選ぶことが重要です。
将来のキャリアへの影響
診療科目によっては、経験を積むことで専門性の高いキャリアを築くことができます。
例えば、がん専門病院の医療事務から医療ソーシャルワーカーへキャリアチェンジするなど、将来のキャリア形成にも影響します。
主な診療科目の特徴と医療事務の業務内容
医療事務の仕事は、診療科目によって業務内容が大きく異なります。
ここでは代表的な診療科目の特徴と、それぞれの診療科目で医療事務として働く際に必要なスキルや知識、業務の特性について解説します。
一般内科
幅広い年齢層の受診者が来院して、多岐にわたる症状に対応します。
風邪や生活習慣病などの日常的な疾患から、専門的な内科疾患まで幅広く対応しています。
医療事務としては受付業務や会計業務のほか、多様な検査や処方に関する知識が求められます。
特に慢性疾患の管理が多いため、定期受診の管理や処方箋の発行業務が中心になります。
消化器内科
胃カメラや大腸カメラなどの内視鏡検査、腹部超音波検査(腹部エコー検査)などの予約管理や検査前の説明などの業務が発生します。
検査の準備から検査後のフォローまで、一連の流れを把握することが重要です。
循環器内科
心電図、ホルター心電図、心臓超音波検査(心エコー検査)などの予約管理を行います。
また高血圧や心疾患など、継続的な治療が必要な受診者のフォローも行います。
緊急対応が必要なケースも多いため、迅速な判断力と冷静な対応が求められます。
特に胸痛や動悸を訴える受診者の場合、緊急性の判断と適切な対応が医療事務にも求められます。
一般外科
手術や処置の予約管理などの業務が発生します。
医療事務としては手術に関連する診療報酬請求の知識、入院の手続きの流れの理解が必要です。
整形外科

レントゲンやMRIなどの画像検査の取り扱いが多く、リハビリテーション部門との連携も求められます。
運動器疾患から交通事故による外傷まで、幅広い症状に対応します。
医療事務としては職場での事故や交通事故による外傷患者が多く来院するため、労災保険や自賠責保険の請求手続きに関する知識も必要になります。
これらの保険制度は一般的な健康保険とは異なる独自の算定ルールがあるため、専門的な対応が求められます。
皮膚科
皮膚疾患の処置や外用薬の処方が中心となる診療科です。
アトピー性皮膚炎や湿疹などの慢性疾患から、急性の皮膚感染症まで様々な疾患を診療します。
医療事務としては、様々な処置や軟膏などの外用薬の算定方法に関する専門的な知識が求められます。
特に処置の種類や範囲による算定の違いについての理解が重要です。
施設形態による診療科目の違いと特徴
医療事務の業務内容は診療科目だけではなく、医療機関の規模や形態によっても大きく異なります。
ここでは、主な施設形態ごとの特徴を見ていきます。
大学病院・総合病院
複数の診療科目が連携して診療を行うため、科目間の調整業務が発生します。
専門性の高い高度医療を提供しているため、難解な医学用語や特殊な治療方法に関する知識が必要です。
紹介状や診療情報提供書の取り扱いなど、地域医療連携に関する業務も多く発生します。
中小規模病院
総合病院と比較すると症例が限定されることが多いものの、入院から外来まで幅広い業務を経験できます。
各診療科目の垣根が低く、柔軟な対応が求められる傾向があります。
診療所(クリニック・医院)
特定の診療科目に特化したクリニックが多く、その分野の専門性を高めやすい環境です。
少人数のスタッフで運営されているため、医療事務だけではなく受診者への案内や電話対応など多岐にわたる業務を担当します。
院長との距離が近く、クリニック全体の運営に関わる機会も多くあります。
キャリアプランを考慮した診療科選び

医療事務としてのキャリアを長期的に考える際には、自分の目指す方向性に合わせて診療科目を選ぶことが重要です。
以下では、代表的なキャリアの志向別に適した診療科の選び方を解説します。
専門性を高めたい
特定の疾患や治療方法に特化したクリニックや専門病院を選ぶことで、その分野の深い知識を習得できるようになります。
専門性を高めることで、その分野のスペシャリストとして評価されて、キャリアの安定性や市場価値の向上につながります。
マネジメントスキルを身につけたい
クリニックなどの小規模な医療機関では、医療事務としての業務だけではなく求人、労務管理、経営サポートなどの業務も任される機会があり、マネジメント能力を養うことができます。
医療業界の幅広い知識を習得したい
総合病院や大学病院など多くの診療科目がある医療機関を選ぶことで、様々な診療科目の特徴や業務を学ぶことができます。
幅広い知識は医療業界内での転職時に強みとなり、今後のキャリア形成の選択肢が増えます。
経験を積むことで様々な選択肢が広がる
医療事務のキャリアは一本道ではなく、経験を積むことで様々な選択肢が広がっていきます。
実務を通じて医療保険制度や診療報酬の知識を深めて、医療機関の運営についての理解度を高めることで専門領域でのキャリアアップや関連分野への展開も可能になります。
初めから明確なキャリアビジョンがなくても、まずは自分の適性や興味に合った診療科目で経験を積みながら将来の方向性を見極めていくことが大切です。
自分に合った診療科目を選ぶために
医療事務への転職を考える際、診療科目の選択は非常に重要なポイントです。
各診療科目の特徴を理解して、さらに自分の適性、興味、将来のキャリアプランを考慮した上で選択することで、より充実したキャリアを築くことができます。
「医療事務の仕事がしたい」という漠然とした希望から一歩進んで具体的にどのような環境で働きたいのか、どのようなキャリアを築きたいのかを考えてみましょう。
D&Mキャリアでは医療事務の転職をサポートするにあたり、診療科目の選択についても丁寧にアドバイスしています。
「自分にはどの診療科目が合っているのかわからない」「特定の診療科目で働く魅力を知りたい」といった疑問やご相談がありましたら、ぜひD&Mキャリアへご連絡ください。
会員登録がまだの方へ
- 転職エージェントからのスカウトが届く
- 非公開求人にもエントリーできる
- 転職サポートを受けられる
他にもさまざまなメリットが受けられます。まずはお気軽にご登録ください。


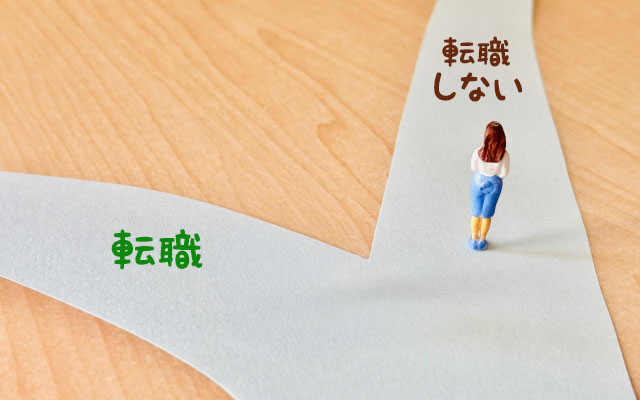

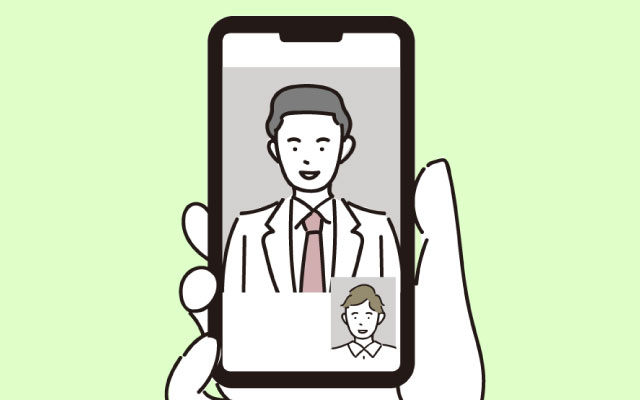

 page top
page top
 会員登録
会員登録
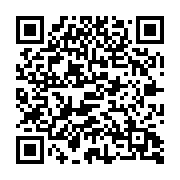



 page top
page top