【特定技能】1号と2号は何が違う?

人手不足解消を目的として2019年に創設された在留資格「特定技能」は、特定技能1号と特定技能2号の2つに分かれています。
同じ特定技能でありながら在留期間や家族帯同の可否、必要な技能レベルなど、異なる点も多くあります。
外国人材の受け入れを検討する際には、これらの違いを正しく理解することが重要です。
本コラムでは特定技能1号と特定技能2号の具体的な違いと、それぞれの特徴について詳しく解説します。
特定技能1号・2号の基本的な違い
まず、特定技能1号と特定技能2号の主な違いを比較表で確認します。
| 特定技能1号 | 特定技能2号 | |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新に上限なし |
| 家族帯同 | 認められない | 条件を満たせば可能 |
| 技能水準 | 相当程度の技能 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4レベル以上必須 | 原則として試験不要 |
| 支援義務 | 必須(登録支援機関への委託可能) | 不要 |
| 対象分野 | 12分野(介護を含む) | 11分野(介護を除く) |
| 永住権取得 | 在留期間にカウントされない | 在留期間にカウントされる |
上記の表からもわかるように、特定技能2号は特定技能1号よりも高い技能レベルが求められる一方で、より多くの権利や自由が認められています。
特定技能1号の特徴
特定技能1号の主な特徴について、在留期間から支援制度まで詳しく見ていきます。
在留期間は最長5年
特定技能1号では、通算で最長5年まで日本に在留できます。
在留カードに記載された期限内(1年、6ヶ月、4ヶ月ごと)に更新が必要で、合計の在留期間が5年に達するとそれ以上の更新はできません。
即戦力として働ける技能レベル
特定技能1号で求められるのは「相当程度の知識または経験を必要とする技能」です。
指導者の指示を理解して、基本的な業務を一人で遂行できるレベルとされています。
12分野で就労可能
介護、建設、農業、外食業など12の分野で就労が可能です。
介護分野は特定技能1号のみが対象となっており、特定技能2号は設けられていません。
日本語能力の確認が必要
日本語能力試験でN4レベル、または国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)でA2レベル以上の合格が必要です。ただし技能実習2号を良好に修了した場合は、この日本語試験が免除されます。
支援が義務づけられている
雇用する事業者は外国人材の生活や就労を支援する計画を策定して、実施することが義務づけられています。
住居の確保、生活オリエンテーション、日本語学習の支援など8つの支援が必要で多くの事業者は登録支援機関に委託しています。
特定技能2号の特徴
特定技能2号では、特定技能1号とは異なる条件と権利が設定されています。
在留期間に上限なし
特定技能2号では在留期間の上限がありません。
3年、1年、6ヶ月ごとの更新は必要ですが、条件を満たし続ける限り何度でも更新可能です。
より高度な技能レベルが要求される
特定技能2号では「熟練した技能」が求められます。
具体的には現場での作業を一人で行えるだけでなく、他の作業者の指導や工程管理を担当できるレベルです。
家族帯同が可能

配偶者と子に限り、条件を満たせば家族を日本に呼び寄せることができます。
家族は「家族滞在」の在留資格で日本に在留して、配偶者は資格外活動の許可を得れば週28時間以内でアルバイトも可能です。
日本語試験は原則不要
特定技能2号の取得にあたり、日本語試験は原則として不要です。
ただし外食業と漁業の分野では、日本語能力試験でN3レベル以上の合格が必要とされています。
支援義務がない
雇用する事業者にに対して、支援計画の策定や実施は義務づけられていません。
特定技能2号の外国人材は、日本での生活や就労において自立していることが前提とされています。
永住権取得への道筋
特定技能2号での在留期間は、永住権取得に必要な「10年以上の在留」および「就労資格での5年以上の在留」の条件にカウントされます。
このため将来的に永住権を取得できる可能性があります。
特定技能1号から2号への移行
特定技能1号から特定技能2号への移行には、以下の条件を満たす必要があります。
実務経験の要件
各分野で定められた実務経験を積むことが必要です。
多くの分野では、管理・指導的な立場での2年以上の経験が求められています。
技能試験への合格
各分野で実施される特定技能2号の技能試験に合格する必要があります。
この試験では実際の作業技能に加えて、管理・指導能力も評価されます。
在留資格変更の申請
試験合格と実務経験の要件を満たした後、出入国在留管理局に在留資格変更の申請を行います。
実務経験を証明する書類の提出が必要となります。
医療・介護分野での注意点
医療・介護分野で外国人材を受け入れる際の注意点について解説します。
介護は特定技能1号のみが対象
介護分野は特定技能2号の対象外となっています。
これは介護分野には別途「介護」という在留資格が存在するためです。
介護分野の外国人材が長期就労を希望する場合は、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」への変更を目指すことになります。
夜間・休日の対応
医療・介護の現場では、24時間体制での対応が必要な場合があります。
特に特定技能1号の場合は登録支援機関による支援が必要なため、夜間や休日にも対応可能な支援体制を確保することが重要です。
どちらの制度を選ぶべきか?

特定技能1号と特定技能2号のどちらを選択するかは、事業者の状況や目的によって判断が変わります。
短期的な人材確保なら特定技能1号
5年以内の期間で人材を確保したい場合や、基本的な業務を担当してもらいたい場合は特定技能1号が適しています。
試験のハードルも比較的低く、技能実習からの移行も可能です。
長期的な人材育成なら特定技能2号
10年以上の長期雇用を前提として、将来的にはリーダーや管理者として活躍してもらいたい場合は、特定技能2号が適しています。
ただし現時点では特定技能2号の取得者はまだ少ないため、特定技能1号からの段階的な育成が現実的です。
コストと手間の違い
特定技能1号では外国人材への支援が義務となります。
そのため事業者が自ら支援を行うか、登録支援機関に委託することとなり一定のコストがかかりますが、特定技能2号では不要です。
一方で特定技能2号の取得には高度な技能と経験が必要なため、人材確保の難易度は高くなります。
今後の制度の展望
特定技能制度は今後も変化していくことが予想されており、その動向について解説します。
特定技能2号の対象分野の拡大
2023年に特定技能2号の対象分野が大幅に拡大されて、建設と造船・舶用工業の2分野から11分野に増加しました。
今後も制度の見直しが継続的に行われる可能性があります。
特定技能2号取得者の増加
特定技能1号で5年間就労した外国人材が、順次特定技能2号への移行を検討する時期を迎えています。
2025年以降は特定技能2号取得者が増加すると予想されます。
制度の特徴を理解した外国人材の活用を
特定技能1号と特定技能2号は同じ特定技能制度でありながら在留期間、家族帯同、技能水準など多くの点で異なります。
特定技能1号は「5年間限定の即戦力」として、特定技能2号は「長期定着可能な熟練者」として位置づけることができます。
どちらを選択するかは、事業者の人材ニーズや育成方針によって決まります。
短期的な人手不足解消には特定技能1号が、長期的な人材育成と組織力の向上には特定技能2号が適しているでしょう。
外国人材の採用の際にはこれらの制度の特徴を理解した上で、それぞれの事業者に最適な選択肢を検討することが重要です。
D&Mキャリアでは特定技能制度に関する詳しい情報提供から外国人材の紹介まで、組織における外国人材の活用をサポートしています。
特定技能制度の活用や外国人材の採用についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。
会員登録がまだの方へ
- 転職エージェントからのスカウトが届く
- 非公開求人にもエントリーできる
- 転職サポートを受けられる
他にもさまざまなメリットが受けられます。まずはお気軽にご登録ください。






 page top
page top
 会員登録
会員登録
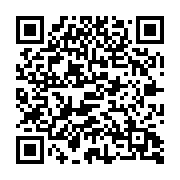



 page top
page top