外国人材とのコミュニケーション|文化の違いを理解して職場の調和を実現する方法

医療・介護現場における外国人材の活用が進む中、コミュニケーションの課題に直面する施設が増えています。
「指示したはずなのに伝わっていない」「休暇申請のタイミングで衝突が起きた」「何度説明しても理解してもらえない」といった声がよく聞かれます。
しかし多くの場合、これらは外国人材の能力や意欲の問題ではありません。
日本人特有の婉曲な表現と外国人材が慣れ親しんだ直接的なコミュニケーションの違いが、誤解や衝突の原因となっているのです。
本コラムでは外国人材との効果的なコミュニケーション方法について、具体的な事例とともに解説します。
日本人と外国人材のコミュニケーションスタイルの違い
外国人材とのコミュニケーションで最初に理解するべきなのは、根本的なコミュニケーションスタイルの違いです。
婉曲表現と直接表現の違い
日本人は相手への配慮から、オブラートに包んだような婉曲な表現を好む傾向があります。
「これはちょっと難しいかもしれませんね」「もう少し考えてみてはどうでしょうか」といった表現は、日本人同士であれば「これは駄目だ」という意味として理解されます。
一方で多くの外国人材は、より直接的なコミュニケーションに慣れています。
彼らにとって「難しいかもしれない」は文字通り「難しいが可能性はある」と解釈されて、暗に込められた否定的なメッセージは伝わりません。
実際の現場で起きている誤解の例
ある介護施設での事例です。
施設長が外国人スタッフに「この業務のやり方、ちょっと違うのではないかな」と伝えたところ、スタッフは「少し違うだけなら問題ない」と判断して同じやり方を続けました。
施設長は「指示に従わない」と感じましたが、実際はスタッフには「やり方を変更してください」という指示が伝わっていなかったのです。
このような誤解は、決して珍しいことではありません。
よく話を聞いてみるとお互いに悪意はなく、単にコミュニケーションの方法が異なっていただけというケースがほとんどです。
「やさしい日本語」の実践方法
外国人材との円滑なコミュニケーションには、「やさしい日本語」の活用が効果的です。
やさしい日本語の基本原則
敬語、尊敬語、謙譲語を避けてシンプルで明確な表現を心がけることが重要となります。
具体的な言い換えの例
- 「お手すきの際にお願いできますでしょうか」→「時間がある時にやってください」
- 「ご確認いただけますか」→「確認してください」
- 「〇〇しておられますか」→「〇〇していますか」
など
指示や要望を確実に伝える方法

外国人材に業務指示を出す際は、以下の点に注意することで誤解を防げます。
明確な指示の出し方
<曖昧な表現を避ける>
- NG:「なるべく早めにお願いします」
- OK:「明日の午後3時までに終わらせてください」
<否定的な指示も直接的に伝える>
- NG:「これはちょっと違うかもしれませんね」
- OK:「これは間違っています。正しいやり方を教えます」
<理由も一緒に説明する>
- NG:「この薬は食後に飲ませてください」
- OK:「この薬は食後に飲ませてください。食前だと胃が痛くなるからです」
質問への対応方法
外国人材からの質問に答える際も、「やさしい日本語」を意識することが大切です。
専門用語を使わず、相手が理解できる言葉で説明することを心がけましょう。
また外国人材が「わかりました」と答えても、重要な指示の後は「今の説明でわからないところはありますか」「もう一度説明しましょうか」と確認することが大事です。
トラブル防止のための事前の確認事項
多くのトラブルは、事前の確認不足から生じています。
採用時や入職時に以下の事項を明確にすることで、後々の問題を防ぐことができます。
休暇取得に関するルール
外国人材との間で最も起きやすいトラブルの一つが、休暇取得に関するものです。
特に母国への一時帰国や宗教行事への参加など、長期休暇の取得を巡って認識の違いが生じることがあります。
事前に確認するべき事項
<休暇申請のタイミング>
- 何日前までに申請が必要か
- 繁忙期の休暇取得の制限
- 連続休暇の上限日数
<一時帰国に関するルール>
- 年間の帰国可能な回数
- 帰国時の最長滞在期間
- 緊急時の例外規定
これらのルールは入職時に文書で示して、本人の理解を確認することが重要です。
口頭での説明だけでは、後で「聞いていない」「理解が違った」というトラブルになりかねません。
給与や待遇に関する認識の統一
多くの外国人材にとって、日本での就労は経済的な目的が大きな比重を占めています。
そのため給与や手当に関する認識の違いは、深刻なトラブルに発展する可能性があります。
明確にするべき事項
- 基本給与と手当の内訳
- 残業代の計算方法
- 社会保険料の控除額
- 寮費や光熱費の負担
- 賞与の有無と支給条件
など
特に手取り額と額面額の違いは、外国人材にとって理解しにくい部分です。
具体的な数字を示しながら、丁寧に説明することが必要となります。
業務範囲と責任の明確化
「これは私の仕事ではない」という認識の違いも、職場でのトラブルの原因となります。
日本の職場では業務の境界が曖昧なことが多い一方、外国人材は明確な職務分掌に慣れていることがあります。
採用時には具体的な業務内容を列挙するとともに、「その他の関連する業務」についても例を挙げて説明することが大切です。
文化の違いから生じる誤解と解決方法
コミュニケーションの違い以外にも、文化的な背景の違いが職場での誤解を生むことがあります。
権利意識の違いへの対応

外国人材の中には、自己の権利を明確に主張する人が少なくありません。
これは決して「わがまま」や「協調性がない」ということではなく、育ってきた環境での当然の行動様式です。
例えば有給休暇の取得について「私には休む権利がある」と主張する外国人材に対して、日本人スタッフが違和感を覚えることがあります。
しかしこれは権利と義務の関係を明確にする文化で育った結果であり、悪意があるわけではありません。
対応方法
- 権利と責任をセットで説明する
- チームワークの重要性を具体例で示す
- 「お互い様」の精神を実例を通じて伝える
など
時間の感覚の違いへの対応
国によって、時間に対する感覚は大きく異なります。
日本の「5分前行動」は世界的に見ても特殊であり、多くの外国人材にとって理解しにくい概念です。
しかし医療・介護の現場では、時間厳守が利用者へのサービスの質に直結します。
なぜ時間を守ることが重要なのか、具体的な影響を説明することで理解を促すことができます。
報告・連絡・相談の文化
日本の職場で重視される「報連相」も、外国人材には馴染みのない概念かもしれません。
特に「相談」については、「なぜ自分で判断してはいけないのか」と疑問を持つ人もいます。
この場合も、理由を明確に説明することが重要です。
「チーム医療では情報共有が患者さんの安全につながる」「一人の判断ミスが大きな事故につながる可能性がある」など、具体的な理由を示すことで理解を得やすくなります。
外国人材との協働がもたらす新たな可能性
外国人材とのコミュニケーションには確かに課題がありますが、それは決して乗り越えられない壁ではありません。
文化の違いを理解して適切な対応を行うことで、むしろ組織に新たな活力をもたらす可能性があります。
重要なのは、違いを「問題」として捉えるのではなく「多様性」として受け入れることです。
お互いの文化を尊重しながらより良い職場環境を作っていくことが、外国人材との協働を成功させる鍵となります。
D&Mキャリアでは外国人材の採用から定着まで、包括的なサポートを提供しています。
コミュニケーションの課題についても、豊富な経験に基づいたアドバイスが可能ですのでお気軽にご相談ください。
文化の違いを乗り越えて、職場の調和を実現するお手伝いをさせていただきます。
会員登録がまだの方へ
- 転職エージェントからのスカウトが届く
- 非公開求人にもエントリーできる
- 転職サポートを受けられる
他にもさまざまなメリットが受けられます。まずはお気軽にご登録ください。





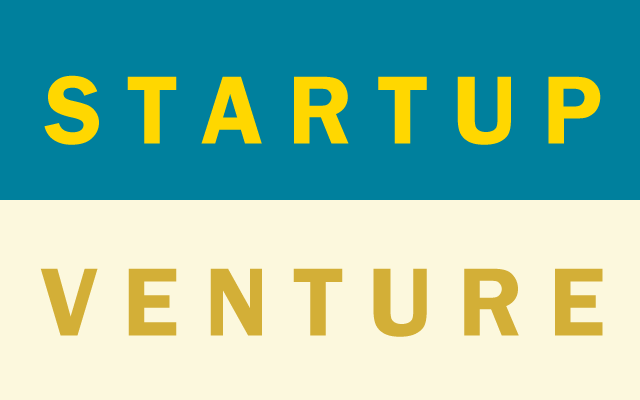
 page top
page top
 会員登録
会員登録
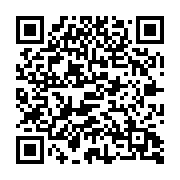



 page top
page top