介護現場で活かせる専門用語・略語の基礎知識
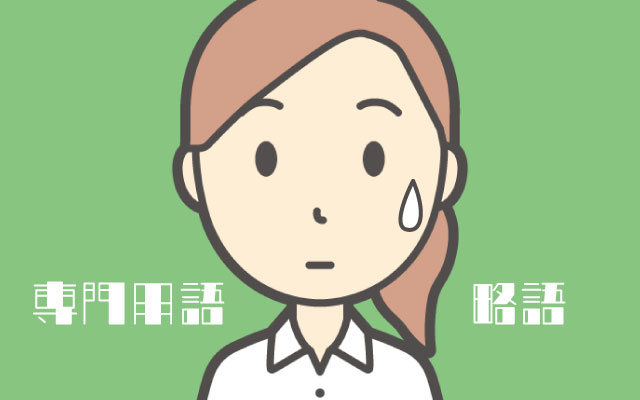
「先輩の話に出てくる専門用語の意味がわからない」
「略語が多くて指示の内容を理解できない」
「申し送りやカンファレンスについていけない」
新人介護職員として現場に出た際、このような不安を感じる人は少なくありません。介護現場では業務を円滑に進めるために、多くの専門用語や略語が日常的に使用されています。
本コラムでは介護現場でよく使われる専門用語や略語について、実践的な解説を行います。
専門用語・略語を理解する意義
介護現場における専門用語や略語の使用には重要な意味があります。
専門用語や略語は単なる業界用語ではなく、質の高い介護サービスを提供するための重要なツールです。特に緊急時の対応や複数の職種が関わる場面では、共通の専門用語を用いることで迅速かつ的確な意思疎通が可能になります。
また利用者の状態を正確に把握して、適切なケアにつなげるためにもこれらの用語の理解は不可欠です。
短時間での的確な情報共有
介護現場では限られた時間の中で正確な情報共有が求められます。例えば「慢性閉塞性肺疾患」を「COPD」と表現することで、素早く正確な情報伝達が可能になります。
多職種連携の円滑化
医療職や他の専門職との連携において、共通言語としての専門用語は不可欠です。お互いの専門性を理解し合い、効果的なチームケアを実現するための基盤となります。
記録業務の効率化
介護記録では限られたスペースに必要な情報を記載する必要があります。適切な専門用語や略語を使用することで、簡潔かつ正確な記録が可能になります。
基本的な施設・サービスの略語
介護施設やサービスに関する基本的な略語から見ていきます。
介護保険制度では多様な施設やサービスが用意されており、それぞれに特徴的な略語が使用されています。これらの略語は施設の特性や提供されるサービスの内容を端的に表現したものです。
新人介護職員にとって各施設の役割や機能の違いを理解することは、適切なサービス提供の第一歩となります。
特別養護老人ホーム(特養)
要介護3以上の方を対象とした介護保険施設です。24時間体制の介護サービスを提供し、長期的な介護ニーズに対応します。
介護老人保健施設(老健)
在宅復帰を目指す中間施設として機能します。医療的ケアとリハビリテーションを組み合わせた支援を行います。
通所介護(デイサービス)
日帰りで介護サービスを提供する施設です。入浴、食事、レクリエーションなどの日常的な支援を行います。
通所リハビリテーション(デイケア)
医療機関や介護老人保健施設で提供される通所サービスです。専門的なリハビリテーションを中心としたプログラムを実施します。
短期入所生活介護(ショートステイ)
一時的な宿泊を伴う介護サービスです。介護者の休息や冠婚葬祭などの際に利用されます。
重要な専門職の略語
介護現場で関わる機会の多い専門職の略語についても理解しておく必要があります。
介護サービスの提供には様々な専門職が関わっており、それぞれが専門性を活かしながらチームとして利用者を支援します。特に医療と介護の連携が重要視される現在では、各専門職の役割や機能を理解し適切なコミュニケーションを取ることが求められます。
介護支援専門員(ケアマネ)

介護保険制度における要となる専門職です。ケアプランの作成やサービス調整を担当します。
理学療法士(PT)
基本的な動作能力の回復や維持を目的としたリハビリテーションを担当する専門職です。
作業療法士(OT)
日常生活動作の改善や自立支援を目的とした作業療法を提供します。
言語聴覚士(ST)
言語機能や嚥下機能の回復・維持を支援する専門職です。
医療ソーシャルワーカー(MSW)
医療機関における相談支援の専門職です。退院支援や社会資源の活用を支援します。
日常的なケアに関する略語
介護現場で頻繁に使用される日常的なケアに関する略語についても解説します。
これらの略語は利用者の状態把握や介護記録に欠かせないもので、毎日の申し送りやカンファレンスでも頻繁に使用されます。特に利用者の生活状態や健康状態を表現する際に使われる略語は、他職種との情報共有においても重要な役割を果たします。
新人介護職員は、早い段階でこれらの略語の意味と使用場面を理解することが求められます。
日常生活動作(ADL)
食事、排泄、入浴など日常生活を送る上で基本となる動作を指します。介護度の判定や支援計画の立案に重要な指標となります。
生活の質(QOL)
その人らしい生活の実現度を表す指標です。身体的な自立度だけではなく、精神的な充実感や社会参加の状況なども含まれます。
バイタルサイン
生命徴候を示す基本的な指標群です。体温(KT)、血圧(BP)、脈拍(P)、呼吸(R)などが含まれます。
医療的ケアに関する用語

医療的な関わりが必要な場面で使用される用語についても理解が必要です。
近年の介護現場では医療依存度の高い利用者が増加しており、医療的ケアの知識は介護職員にとって必須となっています。
特に特別養護老人ホームや介護老人保健施設では、看護職員と介護職員が密接に連携しながら医療的ケアを提供する場面が多くあります。
そのため医療的ケアに関する用語を理解することは、安全で適切なケアを提供するための基本となります。
喀痰(かくたん)吸引
吸引による痰の除去です。介護福祉士または一定の研修を受けた介護職員も実施できる医療的ケアの一つです。
経管栄養
胃や腸に直接栄養を注入する方法です。これも特定の研修を受けた介護職員が実施できます。
褥瘡(じょくそう)
圧迫による皮膚・軟部組織の損傷を指します。予防的なケアが重要となります。
専門用語・略語を効果的に習得するために
専門用語や略語の習得には以下のような方法が効果的です。
介護の現場では数多くの専門用語や略語が使用されており、一度にすべてを覚えることは困難です。しかし体系的なアプローチと日々の積み重ねによって、着実に知識を身につけることができます。
特に新人介護職員は焦らず、自分のペースで確実に習得していくことが大切です。ここでは実践的な学習方法について解説します。
段階的な学習
まずは日常的に使用頻度の高い用語から習得していきます。基本的な施設名称や職種名から始めて、徐々に範囲を広げていきましょう。
実践的な活用
学んだ用語を意識的に使用することで定着をはかります。ただし、使用する際は意味を正確に理解していることが前提となります。
記録による確認
気になる用語はメモを取り、定期的に見直すことで記憶の定着を促進します。特に申し送りやカンファレンスでよく使用される用語は、重点的に確認しましょう。
相談・確認の習慣化
不明な用語があれば、その場で先輩職員に確認する習慣をつけましょう。新人時代は学ぶ姿勢を示すことで、周囲からのサポートも得られやすくなります。
専門知識を活かした質の高いケアの実現に向けて
D&Mキャリアでは、介護職としてのキャリアアップを目指す方をサポートしています。
専門用語や略語の習得は、介護職員としての成長に欠かせない要素です。ただし利用者やご家族との会話では、わかりやすい言葉を選んで使用することも重要です。状況に応じた適切な言葉の使い分けができることで、より質の高いケアが提供できるようになります。
本コラムで紹介した基本的な用語を足がかりに、さらなる知識の習得を目指しましょう。
会員登録がまだの方へ
- 転職エージェントからのスカウトが届く
- 非公開求人にもエントリーできる
- 転職サポートを受けられる
他にもさまざまなメリットが受けられます。まずはお気軽にご登録ください。






 page top
page top
 会員登録
会員登録
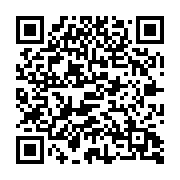



 page top
page top